葉室 麟の「弧篷のひと」を読んで千利久の美意識を高く再認識した次第である。
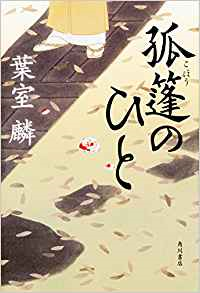
文中に主人公の小堀遠州が利久と黒楽茶碗について話し合う場面が登場する。
もちろんフィクションであるが利久は「黒はあの世の色である。茶道をあの世まで貫き通すために黒楽を作った。」という。
私はこれはあり得ない、物書きの理屈だと思う。
クリエーター利久にとって「黒」が濃茶の緑を一番引き立てる色と分かっているから黒い茶碗をきっと探していたに違いない。
中国の磁洲窯で黒い焼物が作られていたが茶碗ではない。
そんな時に出逢ったのが渡来した陶工「楽長次郎」である。
利久と長次郎、二人の試行錯誤の末に作り上げたのが「黒楽茶碗」だと確信している。

アイディアマンでもあった利久は過去には見たこともない物を茶に取り入れ、創り、大成させたのが侘茶である。
今風に言えば現代アート作家である。
井戸の釣瓶を水指に見立てたり、竹を切って花入れに使ったりと正に現代アートの手法を用いている。
クリエーター利久は過去を安易に踏襲するのではなく自分の眼に適ったものを創り出す才能豊かな人だった。

